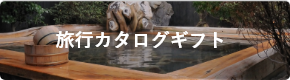入学内祝いののしはどうする?書き方のポイントやマナーについてご紹介

入学祝いをいただいた方に感謝の気持ちを伝える方法として、入学内祝いは大切な役割を果たします。
一方で、のし紙の選び方や表書き、贈る時期など、意外と迷うポイントも多いのではないでしょうか。
本記事では、入学内祝いの基本知識から、いつ贈るのが良いか、宗教や地域による違い、そして「当日返し」の考え方まで詳しく解説していきます。
さらに、myroomのギフトも紹介しながら、入学内祝いをスムーズに準備するコツも併せてご紹介します。
この記事を通して、入学内祝いに関する疑問をすっきり解消し、贈り手も受け取り手も気持ちよく過ごせる素敵なセレモニーに役立てていただければ幸いです。
入学内祝いの基本知識

入学内祝いとは?
入学内祝いとは、子どもの入学祝いとして品物やお祝い金をいただいた際に、そのお礼として贈る品物のことを指します。
多くの場合、入学式のあとに落ち着いた時期を目安に、相手への感謝の気持ちを込めて贈ります。
入学は人生の節目のひとつであるため、いただくお祝いも特別感が大きいものです。
そのため、内祝いを贈ることで「お祝いをありがとうございました。これからも応援をよろしくお願いします」という感謝と挨拶をしっかり伝えることが大切になります。
「のし」はどう選ぶ?表書きは?
入学内祝いに使用されるのしは、紅白蝶結びの水引が一般的です。
結び切りではなく蝶結びを使う理由は、入学のようなおめでたい出来事が何度あっても良いとされるためです。
また、表書きには「入学内祝」や「内祝」と書くのが一般的です。
子どもの名前を記名する場合もありますが、その場合は下段に「○○(子どもの名前)」と記載します。
もし家族として贈る場合であれば、世帯主の名前を書くケースもありますが、近年は子どもの名前を添えることが増えています。
いただいた金額が高額だった場合は、多少豪華なのし紙や包み方を選ぶこともありますが、基本的には相手の負担にならない範囲で、真心が伝わるような配慮が大切です。
入学内祝いの相場と贈り先
入学内祝いの金額相場は、いただいたお祝いの3分の1から半額程度が目安とされています。
ただし、近い親戚から高額なお祝いをもらった場合や、兄弟姉妹同士で習慣化している場合は、金額は目安にしつつ、相手との関係性を考えて決めると良いでしょう。
贈り先は、もちろんお祝いをいただいたすべての方が対象になります。
祖父母や親戚、友人、知人、職場関係など、いただいた方ごとに内容や予算を調整することで、相手の喜ぶ品を選ぶことがポイントです。
入学内祝いの品物選び
入学内祝いの品物は、日常的に使える雑貨や食品が人気です。
例えば、タオルセットやお菓子の詰め合わせ、コーヒーや紅茶などの飲み物ギフトなどが定番となっています。
相手の好みがわかる場合は、それに合わせて選ぶのも喜ばれるでしょう。
また、最近では商品カタログや体験ギフトなど、相手が好きなものを選べるスタイルのギフトも増えています。
相手の年齢や家族構成を考えつつ、負担にならない品を選ぶことが何よりも大切です。
凛【はつにしき】 (3,900円コース)

4,290円(税込み)
和風表紙のオールマイティーな品揃えで安心の定番カタログギフト。
コース最大458ページ・約2280点掲載。
ジャンルに富んだ豊富な品揃えで、ご用途・老若男女を問わずお喜びいただけるカタログギフトです。
最大のポイントは、価格帯・掲載点数ともに業界最大級!
グルメ・温泉・雑貨・ファッション・ブランド品等、業界トップクラスの幅広い商品構成でご満足いただけます。
お好きなものを選べるので、お祝いや内祝いのお返しなど様々なシーンでの贈り物に最適です。
和風の落ち着きのある表紙で、フォーマルな贈り物として人気の高いカタログギフト。
入学内祝いはいつ贈る?

理想的なタイミング
入学内祝いを贈るタイミングは、入学式が終わってから1か月以内が目安とされています。
入学後は何かと新生活の準備で慌ただしくなりますが、なるべく早めに贈ることで相手に対して好印象を与えられるでしょう。
一方で、入学式よりかなり前にお祝いをいただいた場合は、できるだけ入学式後の落ち着いた時期に贈るのがおすすめです。
贈るのが遅くなるほど、相手に「お返しはまだかな?」と気を遣わせてしまうこともありますので、注意が必要です。
入学式前にお礼を伝えたい場合
入学式前にどうしてもお礼を伝えたい場合は、電話やお手紙であらかじめ感謝の気持ちを伝え、正式な内祝いは式のあとに贈るという方法もあります。
この場合、後日内祝いをお贈りしますとあらかじめ伝えておくと、相手も心配にならずに済むのでおすすめです。
ただし、すぐに贈る時間があるようであれば、入学式前に用意を済ませておくのもマナー違反ではありません。
大切なことは、気持ちを早めに伝えることと、贈り忘れがないように管理をきちんとすることです。
地域や家庭の風習にも配慮
入学内祝いは地域や家庭の風習によって、細かなルールが変わる場合があります。
特に親戚関係が多い場合、地方独自の習慣や昔ながらのやり方が重視されるケースもあるので、親や親戚に事前に確認しておくと安心です。
インターネットで一般的なマナーを調べるだけでなく、身近な方の実例を聞きつつ準備をすると失敗を防げるでしょう。
宗教ごとのお祝いの違いとは?

日本ではあまり気にしないケースが多い
お祝いごとに関しては、香典返しなどの弔事と比べると、宗教色はあまり強く意識されません。
日本では多くの人が神道や仏教、キリスト教などを行事ごとに応じて柔軟に取り入れており、入学内祝いも宗教に左右されることは少ないのが現状です。
ただし、クリスチャンの方など一部宗派では、「そもそも”のし”の文化に馴染みがない」という場合もあります。
このような場合は、水引やのしを使わずにシンプルなラッピングで贈るなど、相手の宗教観に配慮した形にすると良いでしょう。
気になる場合は事前に確認する
宗教上、受け取れないものがある場合には、事前に相手から連絡をもらうことが多いです。
しかし、心配な場合にはあらかじめさりげなく「のし紙を付けても大丈夫でしょうか」などと確認しておくと安心です。
特に仲の良い方には、「お子さんの好きなものを選んでいただけるようにカタログギフトでも良いですか」などと希望を聞きつつ、配慮を示すと好印象です。
当日返しとは?

当日返しの考え方
入学内祝いの場面で「当日返し」という言葉はあまり一般的ではありませんが、入学祝いをいただいたその場でお返しを渡すケースもあります。
例えば、入学式に祖父母や親戚、友人が来てくれて、そこで直接お祝いを手渡された場合などです。
この場合は、あらかじめ小さな手土産やお礼の品を用意しておき、式の帰り際などに手渡す方法が考えられます。
ただし、もらった金額を正確に知ってから返したい場合は、やはり入学式後に正式な内祝いを送るのが無難です。
当日返しの注意点
入学祝いをいただいてすぐにその場で返す場合、相手が「こんなに早く用意しているなんて気を遣わせてしまったかも…」と感じることもあります。
そこで、あまり大袈裟な品物ではなく、感謝の気持ちをシンプルに伝える程度のものを準備しておくと、相手に気を遣わせることも少ないでしょう。
また、その場でいただいたお祝いに対してまだ金額を把握していない場合には、一度お礼の言葉だけを伝えて受け取り、後日改めて内祝いを贈るほうが丁寧です。
まとめ

入学内祝いは、子どもの新たなスタートに際してお祝いをくださった方への感謝の気持ちを形にする大切な贈り物です。
紅白蝶結びの水引と「入学内祝」「内祝」の表書きが一般的で、金額の目安はいただいた金額の3分の1から半額程度とされています。
贈るタイミングは、入学式が終わってから1か月以内が理想ですが、いただいた時期や地域の風習に合わせて柔軟に調整するのがポイントです。
宗教による違いは比較的少ないものの、のし文化に馴染みがない方にはシンプルな包装を選ぶなど、相手に合わせた配慮を大切にしましょう。
当日返しは、あまり一般的ではありませんが、実際にお祝いを受け取ったその場で簡単なお礼の品を渡す方法もあります。
とはいえ、多くの場合は事前にきちんと品物を選んで後日改めてお贈りするほうが相手にも喜ばれます。
また、myroomでは入学内祝いにぴったりのギフトを多数取り揃えています。
実際にサイトをのぞいてみると、タオルやお菓子、実用的なアイテム、カタログギフトなど、多彩なラインナップを確認することができます。
ぜひ、贈る方の好みに合った商品を選び、これからの学びを応援してくださった方々へ、感謝を伝えてみてはいかがでしょうか。