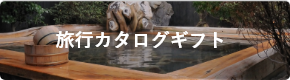【徹底解説】香典返しはいつ贈るのが正解?myroomの厳選ギフトも紹介!

【徹底解説】香典返しはいつ贈るのが正解?myroomの厳選ギフトも紹介!

香典返しを準備するとき、多くの方がまず気になるのは「いつ贈ればよいのか」という時期ではないでしょうか。
大切な方を亡くし、葬儀後の様々な手続きに追われるなか、香典返しのタイミングはなかなか難しい問題です。
さらに、宗教や地域によっては忌明けの日数が異なるため、一概に「何日目が正解」と言い切れない面もあります。
そこで本記事では、香典返しの基本知識から宗教・地域ごとの喪明けの違い、当日返しのメリットや注意点までを幅広く解説いたします。
また、実際に香典返しを準備するうえで押さえておきたい相場や品物の選び方などもご紹介します。
最後までお読みいただくことで、失礼のない香典返しを行うためのポイントが明確になるはずです。
香典返しの時期でお悩みの方は、ぜひ参考になさってください。
香典返しの基本知識

香典返しとは、葬儀や法要の際にいただいた香典に対して、お礼の品をお返しする日本独特の習慣です。
香典をいただいたままにしておくのではなく、喪主や遺族がきちんとお礼を伝えるために贈るのが香典返しの目的です。
しかし、最近では多様な宗教観や地域の風習があり、香典返しのあり方も少しずつ変化しているといえます。
まずは、香典返しの基本的な概要や目的、そして一般的な相場や品物について知っておくと安心です。
香典返しの概要
香典返しは、本来は忌明けのタイミングで贈るものとされています。
仏式であれば四十九日法要を終えてから、神式であれば五十日祭、キリスト教式であれば1カ月後の追悼ミサなど、宗教ごとの大切な節目があります。
ただし、近年では家族葬や直葬などの簡素化も進み、香典返しを「当日返し」という形で済ませるケースも増えています。
「当日返し」とは、葬儀当日に会葬御礼品と合わせて香典返しの品もお渡しする方法です。
こうした形式は地域によっても差があり、どれが正解というわけではありません。
香典返しの目的
香典返しの目的は、弔問や香典をくださった方々への感謝の気持ちを伝えることです。
葬儀は悲しみの最中に行うため、十分にお礼を伝えられないこともあります。
そこで、落ち着いたタイミングであらためて「ありがとうございました」という気持ちを品物に託して贈るわけです。
日本では古くから、いただいた金品には何らかの形でお返しをするという習慣が根付いてきました。
そのため、香典返しも「感謝」と「礼儀」を示す行為として重要視されているのです。
香典返しはいつ贈る?

香典返しの時期は、「忌明けを迎えたタイミング」が最も一般的とされています。
ただし、宗教や地域、そして最近の葬儀事情によっては、当日にお渡ししてしまうケースもあります。
ここでは、一般的な時期と地域差、また早めに贈る場合や遅れてしまう場合の対応について解説します。
一般的な時期
仏式の場合は四十九日の法要を終えてから贈ることが多いです。
四十九日が忌明けの基準とされることが多く、法要の際に挨拶状を添えて香典返しを送付するのが一般的です。
神式の場合は五十日祭を区切りに贈るケースがありますが、十日祭や三十日祭などを目安にする地域もあります。
キリスト教式では、カトリックなら30日目の追悼ミサ、プロテスタントなら1カ月後の記念集会をめどに贈ることが多いです。
このように、宗教によって目安となる日数が異なるため、あらかじめ確認しておくことが大切です。
地域や風習による違い
同じ仏式でも、地域によっては三十五日で忌明けとする場合や、四十九日の後にさらに法要を行う場合もあります。
関西や一部の地域では「満中陰志(まんちゅういんし)」という風習が根強く、四十九日を終えた段階で香典返しを行います。
また、北海道や東北地方の一部では葬儀当日に簡略化した香典返しをお渡しし、後日あらためて贈る場合もあります。
このように、地域や家によって異なる習慣があるため、親戚や葬儀社などに相談してみるとよいでしょう。
早めに贈る場合・遅れる場合
やむを得ない事情で早めに香典返しを贈る場合は、葬儀からあまり日数が経っていない段階で送付することになります。
このときは、挨拶状に「忌明け前ではありますが、感謝の気持ちをお伝えしたくお送りいたします」など、一言添えると丁寧です。
一方、四十九日を過ぎても忙しさや手続きの都合で遅れてしまう場合もあります。
その場合でも、なるべく早めに贈り、挨拶状で事情を伝えれば相手に失礼と感じさせにくいでしょう。
重要なのは、相手への感謝の気持ちを忘れず、きちんとした文面でお詫びとお礼を伝えることです。
宗教ごとの喪明けの違いとは?

宗教によって、忌明けとされる日数や考え方が異なるため、香典返しを贈る時期も変わってきます。
特に仏式では四十九日が有名ですが、他の宗教を信仰されている場合は日数が異なります。
また、同じ仏式でも宗派によっては忌明けの解釈に違いがある点に注意が必要です。
仏式の場合
仏式の多くの宗派では、四十九日が忌明けの目安とされています。
初七日や三七日、五七日など細かく法要が行われることもありますが、四十九日を最終的な区切りと考えるケースが多いです。
一方で、浄土真宗など一部の宗派では三十五日をもって忌明けとする場合があります。
ただし、地域や家の慣習によっては四十九日とするところもあるため、親族やお寺さんに確認するのが確実です。
神式の場合
神式では、五十日祭が忌明けの基準とされることが多いです。
ただし、十日祭、二十日祭、三十日祭と段階的に祭事が行われるため、そのいずれかを目安にする場合もあります。
神式の場合は「忌明け」というよりは「霊前祭」を重ねることで、少しずつ魂を慰めていくという考え方をとります。
最終的に五十日祭で「御霊移し(みたまうつし)」が行われるとされ、それを一区切りと考えることが一般的です。
キリスト教式の場合
キリスト教式の場合、プロテスタントでは1カ月後に「召天記念日礼拝」や「昇天記念日礼拝」を行うことが多いです。
カトリックでは30日目に「追悼ミサ」を行う場合があります。
いずれにしても、四十九日や五十日祭という区切りは存在せず、比較的早い段階で追悼や祈りの儀式が行われます。
そのため、香典返しを贈るタイミングも、キリスト教式の儀式に合わせて1カ月程度を目安にするのが一般的です。
当日返しとは?

最近では、葬儀当日にお渡しする「当日返し」が増えているといわれます。
従来は四十九日を待って贈るのが一般的でしたが、忙しさや簡素化を理由に当日返しを選択するご家庭もあります。
しかし、当日返しにはメリットとデメリットがあるため、事前に十分検討することが大切です。
当日返しのメリット
当日返しの最大のメリットは、香典をいただいた方にその場でお礼ができる点です。
後日改めて送付する手間や送料を削減でき、香典をくださった方も「届いたかな?」と気を揉むことがありません。
また、遺族としても香典返しの管理や発送作業が不要になるため、精神的・時間的な負担が軽減されます。
当日返しのデメリット
一方で、当日返しを行うためには、事前に香典返しの品を数多く準備しておく必要があります。
実際の香典の額と差が生じることもあり、場合によっては不十分な金額相当の品になってしまうリスクがあります。
また、当日にあわただしくお渡しするため、きちんと感謝の気持ちを伝えきれないと感じる方もいるかもしれません。
注意点
当日返しを選択する場合は、あらかじめ参列者の人数や香典の相場を想定して品物を準備する必要があります。
予備を用意しておくのはもちろん、挨拶状やのし紙など、細部まで手配をしておきましょう。
また、当日渡せなかった方や、後日香典をいただいた方に対しては、改めてお礼を送付することを忘れないようにすることが大切です。
香典返しカタログギフト人気ランキング【マイルームギフト編】

それでは、実際にマイルームギフトで取り扱われている「香典返しにふさわしいカタログギフト・ギフト商品」を人気順にランキング形式でご紹介します。香典返しを選ぶ際の参考になれば幸いです。
第1位:香典返しカタログギフト:サユウ【みずがき】(2,800円コース)
香典返しにも送れるカタログギフトとして、落ち着いたデザインとラインナップが魅力です。
価格帯も複数用意されており、いただいた香典の半額~3分の1程度の相場に合わせて選びやすいのが特徴。
内祝い専用のカタログとは異なり、弔事に相応しい表紙のデザインや掲載商品が充実しているため、失礼がなく幅広い年代の方に好評です。
マイルームのおすすめ:サユウ【みずがき】(2,800円コース)
3080円(税込み)
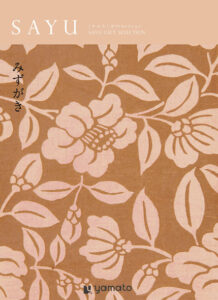
実オーソドックスなアイテムからトレンドアイテムまで、厳選された商品が掲載されたカタログギフトです。どれにしようかアイテムを選ぶ楽しみ、欲しい商品が届く喜びを贈ります。日本の伝統色の名前と表紙で上品さが際立つデザインです。
【おすすめポイント】
・弔事向けデザインで相手に余計な気遣いをさせない
・グルメ、雑貨、日用品などバラエティに富んだ商品ラインナップ
・価格帯が豊富で予算に合わせやすい
【こんな方におすすめ】
・法要や香典返しで何を贈れば良いか迷っている方
・相手の好みがよく分からない方
第2位:有名ブランドが選べるカタログギフト凛【れんぎょう】(4,800円コース)
グルメや雑貨、キッチンアイテムから有名ブランドの小物まで幅広く網羅したカタログギフトです。
「香典返しにブランド品は少し派手では?」という不安があるかもしれませんが、落ち着いたデザインの表紙を採用するなど、弔事にも失礼のない配慮がされています。
選べる商品には有名ブランドのタオルや日用雑貨が含まれており、「質の良いものをお返ししたい」という方に好評です。
マイルームのおすすめ:凛【れんぎょう】(4,900円コース)
5390円(税込み)
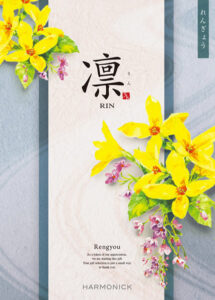
ジャンルに富んだ豊富な品揃えで、ご用途・老若男女を問わずお喜びいただけるカタログギフトです。
最大のポイントは、価格帯・掲載点数ともに業界最大級!
グルメ・温泉・雑貨・ファッション・ブランド品等、業界トップクラスの幅広い商品構成でご満足いただけます。
お好きなものを選べるので、お祝いや内祝いのお返しなど様々なシーンでの贈り物に最適です。
和風の落ち着きのある表紙で、フォーマルな贈り物として人気の高いカタログギフト。
【おすすめポイント】
・有名ブランドの品が多く、品質面で安心感がある
・弔事向けのシンプルな表紙・掲載内容
・手堅いプレゼントとして幅広い年代に喜ばれる
【こんな方におすすめ】
・品質重視で落ち着いた贈り物をしたい方
・「香典返し=実用品を贈りたい」という方
第3位:味にこだわる方に!グルメ特化型カタログギフト
「せっかくならおいしいものを食べてほしい」という方には、グルメ特化型のカタログギフトがおすすめです。
全国各地の名産品や、有名店のスイーツ、日常を少し贅沢にしてくれるお肉・海鮮・スープセットなどが充実しています。
高齢の方やご家族で楽しみたい方には特に喜ばれる傾向があります。
マイルームのおすすめ:彩璃(いろり)【入子菱(いれこびし) HO】(8,900円コース)
9790円(税込み)
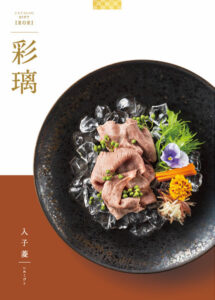
全国各地の名グルメや食材、上質なひとときを演出する味が集まった、美味が見つかるカタログギフト。
コース名は縁起の良い日本の伝統文様で名づけられており、シックな表紙と相まって高級感のあるグルメ専門カタログギフトです。
彩璃(いろり)【入子菱(いれこびし) HO】(8,900円コース)
【おすすめポイント】
・全国の選りすぐりのグルメを掲載
・甘いものが好きな方にも、しょっぱいものが好きな方にも対応可能
・受け取った方の負担が少なく、保管も楽々
【こんな方におすすめ】
・食べ物好きの親戚や知人が多い方
・「形に残るよりも、楽しんで消費できるものを贈りたい」という方
第4位:タオルや寝具など実用品中心のカタログ
ご高齢の方には特に喜ばれる、日用品メインのカタログギフトも人気です。
高品質タオルや寝具、キッチン用品など、生活の中で頻繁に使うアイテムが豊富に掲載されています。
自分では買わないけれど、もらったら嬉しいというワンランク上の日用品が揃っているのがポイントです。
マイルームのおすすめ:テイクユアチョイス【ローズ】(4,900円コース)
5,390円(税込み)
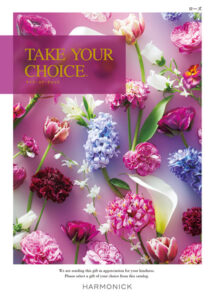
ジャンルに富んだ豊富な品揃えで、ご用途・老若男女を問わずお喜びいただけるカタログギフトです。
最大のポイントは、価格帯・掲載点数ともに業界最大級!
グルメ・温泉・雑貨・ファッション・ブランド品等、業界トップクラスの幅広い商品構成でご満足いただけます。
お好きなものを選べるので、お祝いや内祝いのお返しなど様々なシーンでの贈り物に最適です。
【おすすめポイント】
・実用性に特化しているためハズレが少ない
・タオルや寝具は消耗品でもあり喜ばれやすい
・質の高いブランドタオルや寝具で長く使える
【こんな方におすすめ】
・「使えるものをお返ししたい」と考える方
・年齢層が高めの親族や取引先へのお返し
第5位:マイルームギフト厳選のお茶セット
カタログギフト以外でも、海苔やお茶、スイーツなどの詰め合わせギフトも根強い人気があります。
高級お茶や有名産地の海苔、職人が手掛ける和菓子・洋菓子など、シンプルながら本格志向のラインナップが特徴。
特に法要の場面では、日持ちしやすい食品が好まれます。
カタログギフトと組み合わせて贈る方も多いのが特徴です。
マイルームのおすすめ:お銘茶セット
3240円(税込み)

日本茶など飲み物は、後に残らない「消えもの」の定番です。日持ちする為保存の面でも安心。
【おすすめポイント】
・日持ちする食品がメインで配りやすい
・お茶や海苔は日本の伝統的な贈答品として定番
・お菓子の詰め合わせは老若男女に喜ばれやすい
【こんな方におすすめ】
・気軽に渡せる価格帯の香典返しを探している方
・カタログギフトだけでは物足りないという場合のプラスアルファ
まとめ

香典返しをいつ贈るかは、宗教や地域の習慣、そして遺族の状況によって変わってきます。
仏式であれば四十九日、神式であれば五十日祭、キリスト教式では1カ月程度と、目安が異なるため注意が必要です。
最近では「当日返し」という形で、その場でお礼を済ませるケースも増えています。
ただし、当日返しにはメリットもあればデメリットもあるため、自分の状況に合わせて選ぶことが大切です。
一般的には忌明け後に贈るのが正統とされますが、宗派によっては日数が異なります。
また、地域や家の風習でも変わってくるため、まずは親戚や葬儀社に相談してみるとよいでしょう。
相手に失礼のないように、しっかりと感謝の気持ちを伝えるタイミングを見極めることが重要です。
香典返しは、亡くなった方を悼む気持ちと、香典をくださった方への感謝の心を形にする大切な儀式です。
いつ贈るかをはじめ、どのような品物を選び、どのように挨拶状を添えるかなど、多くのマナーがあります。
本記事の内容を参考に、ぜひ失礼のない香典返しを行っていただければ幸いです。
悩んだときは、専門家や信頼できるサービスに相談するのも一つの方法です。
大切なのは、相手に対して「ありがとう」の気持ちを誠意をもって伝えることだといえるでしょう。