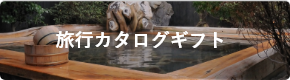今さら聞けない!入学内祝いの贈り方とタブーを完全解説!

入学内祝いは、子どもの入学をお祝いしてくださった方々に感謝の気持ちを伝える大切な行事です。
しかし、何を贈るべきか、いつ贈るべきか、そしてタブーはあるのかなど、いざ準備をはじめると疑問が次々と浮かんでくることも多いです。
入学式は人生において大きな節目であり、それをお祝いしてもらった感謝の気持ちをきちんと形にすることは、相手への思いやりにもつながります。
ところが、入学内祝いには地域や習慣による違いがあるうえ、宗教や慣習によっては注意すべきタブーも存在します。
本記事では、入学内祝いを贈る際の基本的なマナーや時期、そして知らずにやってしまいがちなタブーを解説します。
あわせて、myroomならではのギフト紹介ポイントも織り交ぜながら、ご家族やお子さまが安心して入学内祝いの準備ができるようサポートいたします。
ぜひ最後まで読み進め、正しいマナーとタブーを押さえて、気持ちのこもった入学内祝いを贈りましょう。
入学内祝いの基本知識

そもそも「入学内祝い」という言葉が生まれた背景には、入学という人生の節目を祝福していただいた方へのお礼が関係しています。
一般的には、子どもが小学校や中学校、高校、大学など、ステップアップとなる学校へ入学したときに、お祝い金やお祝いの品をいただいた場合に「内祝い」を贈る習慣が根付いています。
「内祝い」とは、もともと「お祝い事があった家が、親戚や近所の人などにおすそ分けのような形で配るもの」という意味があり、自分たちの幸せのお裾分けという考え方からきています。
しかし現代では、お祝いをいただいたことに対する「お返し」という意味合いが強くなっています。
そのため、入学内祝いについても「入学祝いとして何かをいただいた場合、その感謝の気持ちを品物や金銭でお返しする」という考え方が基本です。
入学内祝いとは
入学内祝いは、入学式が終わった後に「お祝いをくださった方へ」感謝の品をお贈りすることを指します。
正式には「内祝い」ですが、何の内祝いかを明確にするために「入学内祝い」と呼ばれることが多いです。
特にお祝い金をいただいた場合は、その金額に見合った品物やギフト券などをお返しするのが一般的です。
ただ、地域性や家庭の考え方によって、「お祝い金に対して半額程度を目安に返す」という方もいれば、「金額はあまり気にせず、気持ちを重視して選ぶ」という方もいます。
基本的にはお世話になった方への感謝を表すものであるため、価格や品物選びには相手が喜びそうかどうかをしっかり考慮することが大切です。
入学祝いと内祝いの違い
「入学祝い」は、子どもの入学をおめでとうという気持ちを込めて贈る金銭や品物のことを指します。
一方、「内祝い」は、先にいただいたお祝いへのお礼や感謝を形にしたお返しです。
つまり、入学祝いを受け取った側が、改めて「ありがとうございました」という気持ちを込めて用意するものが入学内祝いというわけです。
このように、贈られるタイミングや目的が異なるため、混同しないように注意しましょう。
入学内祝いはいつ贈る?

入学内祝いを贈るベストなタイミングは、入学式が終わった直後から1か月以内といわれることが多いです。
なぜなら、入学式が終わってからあまり日にちが空くと、受け取った側も「忙しくて忘れてしまったのかな?」と思うかもしれません。
一方で、入学式直後は学校の準備やお子さまの新生活対応などで何かと慌ただしい時期でもあります。
そのため、落ち着いてから準備を進めるには1〜2週間程度を目安にするとスムーズでしょう。
特に遠方の親戚や友人など、直接会って手渡しできない場合は配送も考慮しなければなりません。
早めに準備して、入学式の1週間後くらいから送付開始するのも良いタイミングです。
贈るタイミングのポイント
入学内祝いを贈る具体的な目安は「入学式後1か月以内」ですが、お祝いをいただいたタイミングによっては調整が必要です。
たとえば、入学前に前渡しでお祝い金をいただいた場合は、入学式が終わって一息ついたら早めにお返しを準備すると相手に好印象を与えます。
また、入学式が終わったばかりの時期は何かとバタバタしやすいので、のしや梱包、配送手配もあらかじめ計画的に進めることが大切です。
渡し方のポイント
入学内祝いを直接手渡しするのが理想ですが、遠方や都合が合わない場合は配送を利用しましょう。
配送の場合は、必ずメッセージカードや手紙を添えることで感謝の気持ちを一緒に伝えることができます。
とくにお子さまの写真入りカードや手書きのメッセージなどがあると、より相手にとっても「お祝いして良かった」と感じてもらいやすいです。
myroomでも、ギフトと一緒にメッセージカードを同梱するサービスなどがありますので、ぜひ活用してみてください。
入学内祝いと宗教・地域のマナー

入学内祝いは基本的にお祝いの延長線上にあるものですが、実は宗教や地域によってマナーが変わることがあります。
といっても、慶事の場合は喪中や忌明けのような厳密な制限は少ないため、冠婚葬祭と比べるとそこまで大きく異なるケースは多くありません。
しかし、贈る側としては念のため、相手の宗教観や地域の習慣を気にかけることが大切です。
特に食べ物を贈る場合は、原材料や調理過程に宗教的なタブーがないか注意しましょう。
また地域的に「この品物は縁起が良くない」とされる風習があれば、避けるのが無難です。
神式・仏式・キリスト教の場合
入学内祝いで宗教的な制約が気になるケースは少ないですが、送る相手が特定の宗教に深く帰依している場合は事前のリサーチが重要です。
たとえば、仏式では特に気にされない場合が多いものの、地域によっては入学後しばらくはお祝いを控える習慣があるかもしれません。
キリスト教圏の方でも日本の文化に理解がある方がほとんどですが、もし相手が海外在住であれば、渡航制限や通関の問題にも配慮する必要があります。
神式の場合は、あまり贈り物に対してタブーという概念が強くないものの、品物の選び方やのし紙の表書きには気を付けるのが望ましいです。
地域による違い
地域によっては「お祝い事には必ず赤飯を配る」「菓子折りを配るのが習わし」というような伝統が根付いていることがあります。
入学内祝いも同様に、お住まいの地域のしきたりに合わせた品物を選ぶと、相手にとって好印象になるでしょう。
とくに近隣の方へのお返しであれば、昔ながらの風習に従うほうがスムーズな場合もあります。
遠方の方に贈る場合は、その地域特有のマナーがないか確認するか、無難な洋菓子やタオルセットなどを選ぶのも一案です。
もし贈り忘れたら?当日返し(当日渡し)の考え方

入学内祝いではあまり聞き慣れないかもしれませんが、「当日返し」という言葉があります。
本来は香典返しなどで、葬儀や法要の当日に返礼品を渡す習慣を示す用語です。
しかし入学式や卒業式の場合でも、当日に直接お祝いをいただくことはあり得ます。
こうしたとき、急いでお返しを用意する必要があるかどうか、迷う方もいらっしゃるでしょう。
結論からいうと、入学式の当日にお祝いを受け取った場合でも、その場で返礼品を渡す文化は一般的ではありません。
むしろ落ち着いたタイミングで、後日きちんとお礼の品をお送りするのがマナーとされています。
当日返しとは
本来の意味での「当日返し」は葬儀関連で使われる用語ですが、「いただいたその日に即返す」という発想を指すこともあります。
ただし、入学内祝いについては、式当日は家族やお子さまも新生活の準備でバタバタしているため、余裕がないケースがほとんどです。
そのため、当日返し自体を考える必要は薄く、落ち着いてから改めて感謝の品を贈るのが一般的といえます。
緊急時のマナー
もしも当日に予想外の金額や品物を受け取った場合、慌てずにお礼だけは口頭でしっかり伝えることが大切です。
そのうえで、「後日改めてお礼を送ります」とひとこと添えれば、相手も安心して待っていてくれるでしょう。
当日返しを無理に用意して、バタバタと手渡しをしてしまうよりも、落ち着いた状態で相手の好みや状況に合ったギフトを選ぶほうが、結果的に気持ちの伝わる入学内祝いになります。
myroomでは豊富なギフトラインナップを取りそろえているため、ゆっくり考えて選ぶ余裕を持てるのも魅力の一つです。
まとめ

入学内祝いは、子どもの新たな門出をお祝いしてくださった方への大切なお返しです。
贈り物を通じて「ありがとうございました」「これからもよろしくお願いします」という感謝と今後の関係を円滑にする思いを伝えることができます。
一方で、入学内祝いには地域や宗教、あるいは品物選びなどのタブーやマナーが存在します。
特に注意したいのは、相手の立場や好みに合わないものを贈ってしまうケースや、タイミングを逃してしまうケースです。
本記事で解説したポイントを押さえておけば、失礼のない入学内祝いを贈ることができるでしょう。
また、myroomのギフトを活用すれば、豊富な品揃えやメッセージサービスによって、より心のこもったお返しが可能になります。
お子さまの大切な人生の節目を祝っていただいた気持ちにしっかりと応えるためにも、ぜひ正しいマナーとタブーを理解し、スムーズに準備を進めてください。